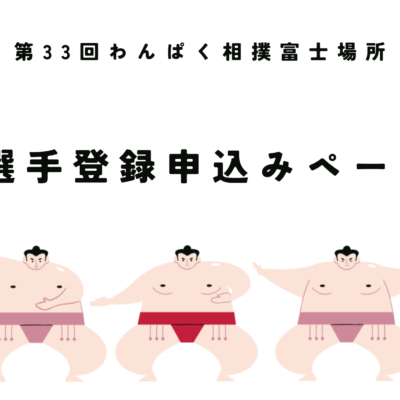目次
はじめに
大きく時代が変わっても、譲れない想いがある。譲れないことがある。
この数年のコロナパンデミックは、我々の日常も大きく変容させた。世間の情勢によって変化を迫られる。
考え方や価値観が変わり、自ら変化を決断する。人との付き合い方や働き方、お金の使い方や余暇時間の使い方など、様々な日常において、以前とは違った日々を過ごしている方は少なくないのではないだろうか。
新たなビジネス、新たな技術の台頭。当たり前が当たり前じゃなくなる。常識が時代遅れと呼ばれる。
発展とイノベーションによって急速な変化を迎えていた現代において、新型コロナウイルスの蔓延はその 動きを更に加速させました。
「人間、ともすると変わることにおそれをもち、変えることに不安を抱く。しかし、すべてのものが刻々と変化する今日、現状に安んずることは、即、後退につながる。」経営の神様と呼ばれた松下幸之助氏の言葉である。
我々一人ひとりがビジョンを描き、より良い変化をもたらす力を育て行動し続けることで、明るい豊かな社会が実現すると、私は信じている。多くの決断の中で、我々の譲れない想い、譲れないこと、変えるべきものは何なのか。その本質を見極め、目的を見極め、熱を持って、恐れず前進しよう。
我々の描く明るい未来のために、明るい豊かな社会のために今、挑戦しよう!
3 信条・SDGs で育む 富士市の
未来に花開く希望の種を蒔こう
我々、富士青年会議所は昨年、65 周年の節目を迎えました。この世の中を少しでもより良くしたい。そんな想いから行動された諸先輩方に感謝すると共に、創始の精神を忘れず挑戦し、前に進んでいこう!
まちの未来を創る青少年の育成
まちの未来を創る子どもたちのために、心に残る体験を。
成功体験、失敗体験、感動体験、原体験。子どもの持つ、無限の可能性を花開かせるためには多くの体験 が必要です。様々な機会が少なくなり、コミュニケーションも抑制されることが当たり前になってしまった今、直接体験の機会は更に減少しています。子どもたちが、将来自ら課題解決していくために、必要な力と心を養う機会を、我々が創出しよう。失敗を恐れず、挑戦した体験は子どもたちの明るい未来を創ると私は信じている。子どもたちの未来のために、私たちも挑戦していこう!
魅力溢れる人財の育成
魅力ある人財に支えられた、魅力ある組織に。
昨今の複雑な課題に対応していくためには、我々自身の資質向上はもちろんのこと、パートナーと連携すると共に、更に多くの仲間を募ることが必要です。魅力的な人財は組織を活性化させ、人を惹きつける。
我々が明るい豊かな社会の実現に向けて挑戦し、自ら変革し続けていくことで、他者の共感を得るとともに、 協動する仲間を増やすことができると私は信じている。自身の描く明るい未来のために、明るい豊かな社会 のために、多くの成長の機会を創出していこう!
まちの未来を創造する
想い溢れる人々が創る、明るい未来のまちづくりを。
富士市は他自治体の例に漏れず、人口減少や少子高齢化、競争力の低下など、多くの課題を抱えている。
魅力溢れる持続可能なまちにしていくために必要なことはなんだろうか。青年経済人としてビジネスを通じてまちの未来を創るだけでなく、賛同者を増やしていくことも必要である。まちの課題を共有し、自分事 に捉え、まちへの溢れる想いを持って、より良いまちの未来を創造する。未来に向かって挑戦する市民が一 人でも増えていくことが持続可能な明るいまちの未来に繋がると私は信じている。まちを想う、共創する仲間を一人でも多く増やしていこう!
会員交流と国際の機会
絆を育み、架け橋となろう。
諸先輩方が繋いでこられた、富士青年会議所 65 年の挑戦の歴史を我々はどれだけ知っているだろうか。
姉妹 JC との交流の歴史を我々はどれだけ知っているだろうか。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉がある。この財産とも言える歴史を、絆を育む中で学ぶと共に、多くの仲間とその想いを共有しよう。そして我々の活動を支えてくれている家族や会社の存在も忘れてはならない。見えない活動に理解は生まれない。感謝の気持ちを持ち、絆を育む架け橋となるべく活動していこう!
魅力が伝わる、見える広報
ストーリーが伝わる、魅せる広報。
JC しかない時代から JC もある時代に変わったと一昔前から叫ばれている。様々な意見はあるが、多くの団体が誕生したことは事実だと思う。多くの情報が溢れ、選択肢も無数にある現在、良いものが何もしなくても売れるという時代ではない。我々の運動や活動も、その目的を十全に果たすためには、しっかりと伝え
たい人に伝わることが大切である。目的意識と当事者意識を持ち、運動や活動に対する想いやストーリーと共に、熱のある情報を戦略的に発信しよう。伝わる広報の仕組みを創るべく、挑戦していこう!
持続可能な組織運営
様々な価値観を受け止める、持続可能で盤石な組織運営を。
青年会議所が会議体であり組織である以上、多くのルールや必要なことが存在します。定款や各種規定を厳守しつつ、その定められた目的をしっかりと把握した上で、凛とした運営を期待する。
新型コロナウイルスの影響から我々は「オンライン」や「ハイブリッド」という選択肢を手に入れた。メリットもデメリットもあるが、大きな変化であったことは事実である。本質を見失うことなく、様々な個性を持つメンバーが活動しやすい組織運営を目指し、変化を恐れず挑戦していこう!
結びに
1969 年 7 月 20 日。アポロ 11 号が人類で初めて月に着陸し、人類の夢を現実に変えました。夢にしか思えなかったであろう、宇宙への道を拓くきっかけとなった開拓者は誰だったのだろうか?様々な意見はあるが、私はファンタジー作家のジュールベルヌ氏だと考えている。彼の書いた小説「月世界旅行」は発刊さ
れた 1865 年以降、多くの技術者を魅了した。「宇宙旅行の父」ツィオルコフスキー氏や「液体燃料ロケットの父」ゴダード氏をはじめ多くの技術者がジュールベルヌ氏の描いた未来に魅せられ、賛同し、そこに向かって歩みをとめず挑戦し続けた。その結果、発刊から 104 年たった現在、宇宙ビジネスとして民間の旅行が現実化している。
青年会議所の使命は、発展と成長の機会を提供し続けることで、自ら運動を起こせる能力を持った人財を増やしていくことにある。そしてその先で、一人ひとりが描く、明るい豊かな社会が築かれると信じているのである。ジュールベルヌ氏が小説の中で自身の夢を現実として描いたように、我々にもそれぞれが願う、
理想の明るい豊かな社会がある。その目的を達成するために、誰かがやるのを待つのではなく、自分事として行動し、挑戦し続けていく人財が集まり、富士青年会議所は誕生した。今もそれは変わっていないと、私は信じている。
月世界旅行の未来は、当時では果てしない夢物語でした。しかし、人の熱意はその夢を現実のものにしたのです。我々の描く明るい豊かな社会は永遠に続く夢物語のようなものなのだろうか?私はそうは思わない。たとえ今は夢物語と思えるような未来も、その目的に向けて挑戦し続けていけば、必ず実現することが
出来る。私はそう確信しています。
目的を持ち、発信し、賛同者を募り、共に成長しよう。
自分のため、家族のため、会社のため、地域のため、未来のために。
富士青年会議所にはそのための仲間がいる。そのための成長の機会がある。そのための運動・活動がある。
挑戦できる環境がある。
2023 年度、富士青年会議所の理事長をお預かりする立場として、私はその機会の提供を約束する。
変化を恐れず、一歩を踏み出そう!
未来へ挑戦しよう!!
基本理念
変化を恐れず創ろう、自分の未来
一人ひとりの想いを紡いで創ろう、まちの未来
基本方針
◆ 目的意識を持って、より良い変化をもたらす機会の創出。
◆ リスペクトを忘れず、仲間や地域との絆を育む。
◆ 未来を創る青少年の心に残る運動を起こす。
◆ パートナーと共に、まちの未来を共創する。
◆ 見える広報、魅せる広報を通じて地域にインパクトを。
◆ 誰かだけに頼らない、持続可能な組織運営を。
◆ より良い未来のために、全員で多くの仲間を募る。
LOMスローガン
「共栄共創」
未来へ挑戦しよう!!